協調性と共感性は全く別物ですが、混同されがちなので違いを解説していきます。
『共感性がある=協調性がある』ではありません。
どちらの要素を持っている人もいれば、片方しか持っていない人、両方持っていない人と様々です。

この記事を書いた内向型HSPのふゆです。
HSPは共感性が高い特徴があります。
私は共感性が高いのですが、協調性があるかどうかは微妙なところ。
目立たないように協調性を発揮しているつもりが、
場の空気を取り乱して逆に目立ってしまうことも…
2つの違いとメリットの活かし方を解説します!
・協調性より共感性が重要視される理由
・共感性が強すぎる人の注意点
HSPの人は共感性が高い

HSPとは、「Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)」
生まれつき「非常に感受性が強く敏感な気質をもった人」です。
HSPの特徴として、「人の気持ちに振り回られやすく、共感力が高い」が挙げられます。
共感性についての記事も書いているので、詳細は参考記事を見てみてください!
共感性と協調性の違いとは
協調性:性格や意見が違うもの同士が互いに譲り合って協力できる能力
共感性は、自分の意見を尊重しつつ、相手の意見も受け入れて共感することです。
協調性は、自分の意見を押し殺して、周囲に合わせる事もあります。
協調性も大切だけど、共感性を高めよう
協調性が強すぎると、人間関係でストレスを抱えてしまう事があります。
協調性の「相手に合わせる」事が苦痛となり、
知らず知らずに自分の個性が発揮できない苦しさを感じているかもしれません。
「協調性がない」事は短所に捉えられがちですが、無理に協調性を高める必要はありません。
みんなが幸せになれる、相手に寄り添う「共感性」を高めることをおすすめします。
協調性のメリット
協調性が重要視される場面は多くあり、学校では協調性を持つ大切さを教えられました。
- 周囲に合わせた行動をする
- 場を乱して周囲に迷惑をかけない
- みんなで協力する
集団行動をする際には、協調性が重要視されます。
協調性がないと、輪を乱すことになり、周囲に迷惑をかけてしまいます。
協調性のデメリット
協調性を意識しすぎるとストレスが溜まることがあります。
- 周囲の目が気になり、自分の意見が言えなくなる
- 目立つのは良くないと刷り込まれ、個性が発揮できなくなる
- 同調意識が高まり、周囲の意見に流されやすくなる
協調性がない人の特徴は頑固で単独行動を好み、他人に興味がないなどが挙げられます。
私はこの全てに当てはまるのですが、内向的な性格の人は協調性が低い傾向にあるようです。
共感性のメリット
人に共感されると誰でも嬉しく感じます。
相手の気持ちや意見を理解して、受け入れる思いやりの心は大切です。
相手が楽しんでいる時には一緒に楽しみ、
悲しんでいる時には、話を聞いてあげて悲しみを共感します。
相手の心に寄り添ったことで感謝されると、自分まで嬉しくなりますよね。
これが他人に共感できるメリットです。
共感性が高すぎる人は要注意(デメリット)

共感性が高い人は感受性も高い傾向にあり、感受性が高すぎると感情的になる時があります。
感受性が高すぎる人は以下の点を注意しましょう。
ちょっとしたことで傷ついたり、自己否定をしてしまうことも。
合わせて感受性があるので、感受性が高すぎると短所になってしまいます。
自分と他人の間に境界線を引き、引きこまれそうになったら一歩引く心掛けを。
自分の軸や芯をしっかり持っておくことも大切です。
まとめ
共感性と協調性は異なります。協調性は教育上義務感が乗っかている。
HSPの人は共感性が高いが協調性が低い傾向がある。
共感性が高く、感受性が高い人は周囲の意見に流されないよう自分の軸を作ろう
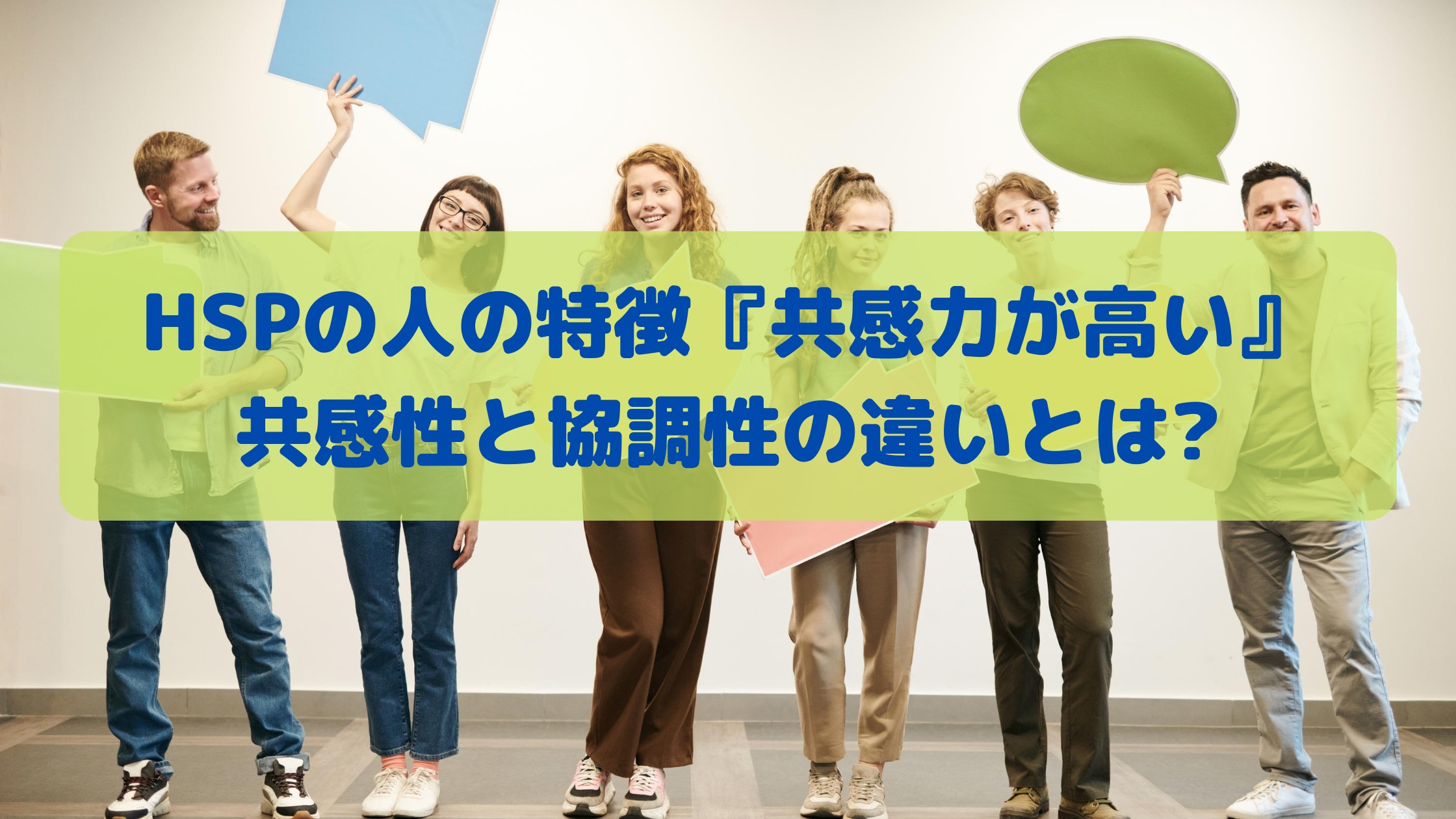
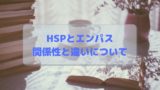
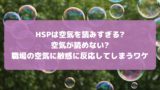

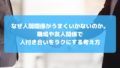
コメント